|
|
|
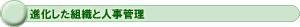 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
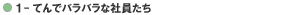
わが社の社員たちがどんな勤務行動をしているか、管理職は掴んでいますか。
たとえば営業なら顧客対応や提案、訪問や拡販計画などを部下がせっせとしていますか。お客様が何を求めているか、わが社がどう対応すれば喜んでくれ、販売につながるか真剣に考えているはずです。
製造なら製造で、良質な商品を出すよう懸命なはずで、お得意先からの発注に納期の遅れをださないよう、計画生産に励んでいるでしょう。さらに低価格で仕入れるようコスト意識もなくてはなりません。
こうした「期待される行動」と「現実の勤務内容」とが一致しているかどうかをチェックするには、本人からの「自己申告制」と、同僚や上司。部下を交えた「多面観察」しかありませんでした。
両者は一長一短があって、どちらも使うことで補完している会社が多いようです。ただ、自己申告制はどうしても己に甘くなり、上がってきた各自による自分自身への目標づけと通信簿の確認と調整のために人事部が苦労してきました。部門内と部門間との二重の調整が必要でした。
本人をとりまく同僚らが評価しあうという多面観察は、対象者が何を目標にしてどう行動しているか詳細には判らないため、どうしても曖昧な評価が入り込んでしまい、好き嫌いの側面が強くでてしまいます。客観的判断にはほど遠いのが現状なのです。
社員たちは、それぞれに課題に向かってベストを尽くしているように何となく見えます。
が、よくよく調べてみると各社員たちの行動はてんでバラバラな状態であることが多いのです。
業務日報を分析してみました。
ここでは営業部門のケースの話をします。
日報には、社員たちが「顧客」ごとにどのように「対応」し、お客様が求めていることに対してどういう「提案」といているか記述していました。
お客様がいまのわが社に対して、価格や品質、サービス態勢などにもしも不満や苦情があるようならば、それはどんな「問題点」なのか、どう「改善」すればいいのでしょう。そうして「維持」できて従来どおりのお取引を願えるのでしょうか。
万が一、こちらの提案が受け入れられず、あるいはライバル会社からの提案の方を採用され、相手方に取られたのなら何が流出原因だったのでしょうか。
反対に、わが社のほうがライバル社のお客様をターンオーバー(奪取)し、新規の顧客として「獲得」でき取り込めたとき、そこにはどんな誘引や事情があったのでしょうか。
そうしたことを日々の業務日報に書き込んでいました。
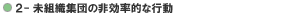
私たちの特許である文章解読技術をもちいたところ、組織にはいろいろな活性化の段階があることがわかりました。
社員たちがまったく組織目標を理解できず、てんでバラバラな活動をしているところは組織そのものも元気がなく、経営的にも苦労していました。
業務日報に書かれた記述内容はコトバの羅列というか、なんの法則性もなく、個々人が思いつくまま、考えられるままに行動していたことが明白でした。本人にとってはベストな行動と営業対応していたツモリでしょうが、組織としてはまとまりが見られませんでした。
社員ひとりずつの才覚で動いていたわけで、これでは「暗黙知」の段階です。
実力1のAさんと実力2のBさんがいる東京営業課と、実力2のCさんと実力2のDさんがいる北関東営業課では、どちらが実力が上でしょうとか論じているレベルです。組織以前のハナシで、どちらもダメなのです。
組織とは 1+1=10 にもなりえて、1+1=0 にもなりうる不思議な人間の集団なのです。
実力が足し算のままでは、その集団は組織になれていません。ただの群れです。ですから、知識やアイデアも個々人のレベルでしかなく、組織行動にいたっていないのです。もったいない。
業務日報がこんな状態だとしたら、そんな管理職は失格です。
放置・放任でのんきに構えていたのです。
経営トップの責任でもあります。
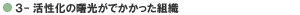
「こんなことではイカン!」「もっとしっかりお客様のことを考えろ」とか言われだし、トップや管理職が部下に発破をかけはじめるようになると、社員たちの行動に変化が見られます。
顧客対応や提案活動、顧客獲得や維持のための活動が活発になり、有効な作戦というものが頻繁に出てくるようになります。社員たちがコツを飲み込め、どうやったら効果的なのか伝わってきだしたのです。有効な作戦は仲間にもヒントになりますから、それは社内でしょっちゅう使われる行動となっていきます。
多頻度「対応」となるわけです。
個々人の才覚やたまたまのアイデアだった「暗黙知」から「形式知」にと発展しはじめたのです。組織に認められてきたために、その作戦というか対応はみんなの智恵=財産になったのです。
その業界とかあの団体に特有な知識や反応、対応、考え方というレベルにまで行きました。多次元尺度法(MDS)という計算をもちいると、多用される言葉は外側に広がって並びます。私たちの読解技術をMDSにかけたものが図2です。外側に拡大した配列は環状星雲のようでしょう。
ただし、まだ惜しいかな、しばしば出てくる行動や対応であるのだけれど、それらの中にはは相互に関連性が少ない語もあります。
まだ頻度のレベルなのです。永田町コトバとか、霞が関用語とか、築地符丁といわれる段階です。よく用いられる言葉と、そうでない言葉とが弁別できてきだしたところです。

「これは使える手だ」と理解できた対応方法が、しだいに組織内に普及していくことは、智恵の共有化に欠かせません。人が人材から人財になる一歩です。
でも頻繁に使われる対応方法がリスト化されただけでは、まだまだ「財」にはなりきっていません。毎回、トラブルの発生や問題が起こるたびに「どうしたらいいか」頭を抱えるようではいけません。
この問題にはこの対応をと決まっていなければ顧客は面くらいます。そのうちに今回は「この対応にこれを加味して」と変化球もつけられるようになると、顧客の新たな要求がどこへんにあるか知る手がかりにもなります。
いずれにしろ、この問題にはこれとこれが有効なこと。その問題は必ずアアすべきことが定着すること。
こうした対応は顧客からキチンとして対応とみなされ、安心します。ISOでいうところの確定したサービスです。
この会社は顧客対応について着実な進化の途上にあります。
例えば1000人の営業マンが毎日、帰りにこうした業務日報を書き込んでくれるだけで、それぞれが見聞きし、集めたた情報が組織の共有財産として確保されるのです。なおかつ、わが社の対応として世間から安定的な評価を与えられるようになります。
社員の個々人が、その歩んできた経歴や経験で「それとなく」思っていた知識が共有化されます。暗黙知が形式知に昇華し、またわが社の組織としての営業知として「金を生む木」になってくれるのです。この図の会社は、一年前の「てんでバラバラな」勤務行動から、業務日報の活用によって営業効果をあげられるようになりました。
5つの対応パターンの存在が認識でき、入社浅い新入社員や他社からの転進組もが、ベテランと同じ職務をこなせるのです。そうなると、階級の高い、無駄な高層式のピラミッド型組織は要らなくなります。コスト削減効果だけでなく、社員にほんとうの業績配分ができるようになり、勤務評価と配分についての不満がなくなるでしょう。 |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
